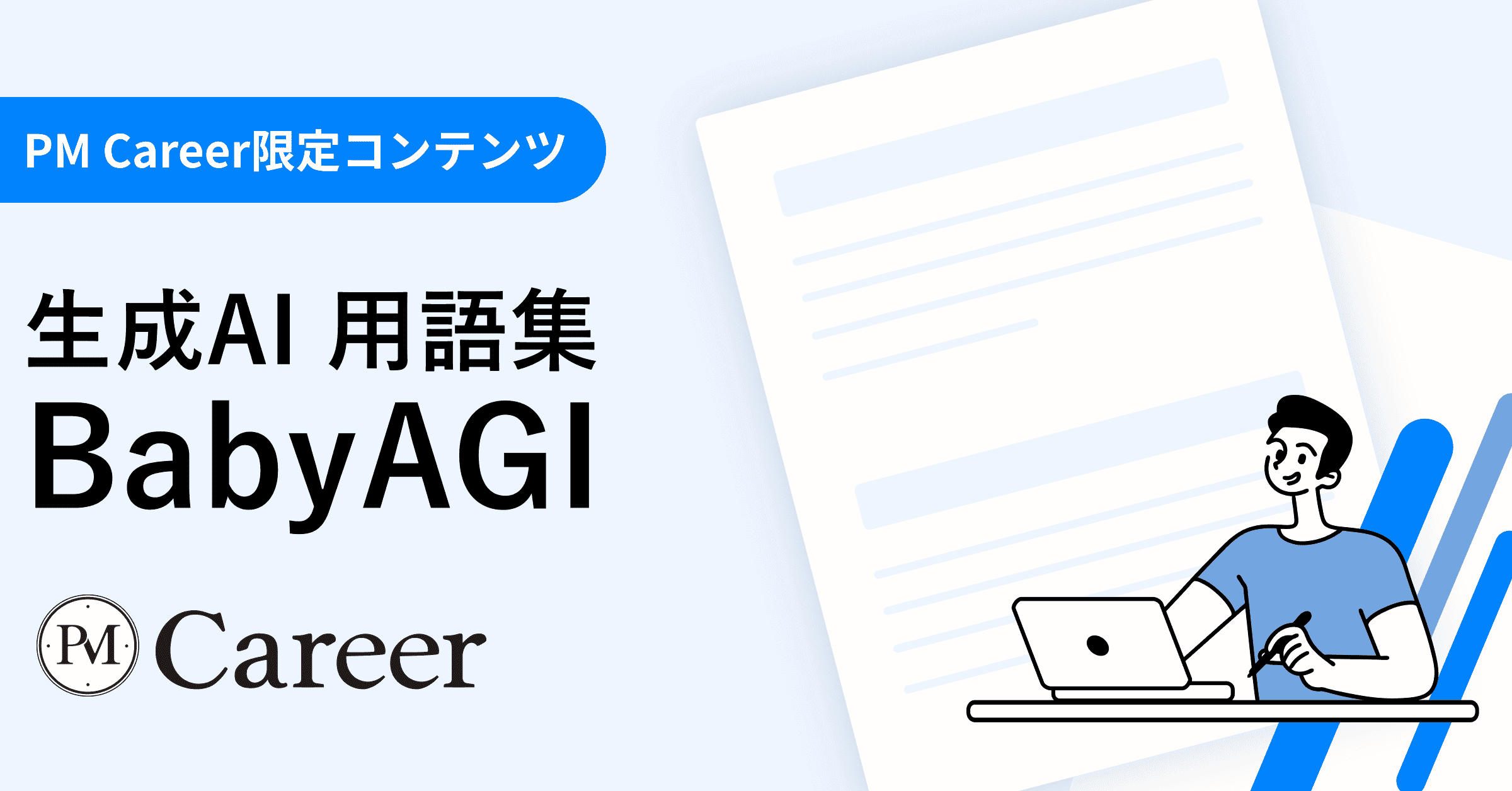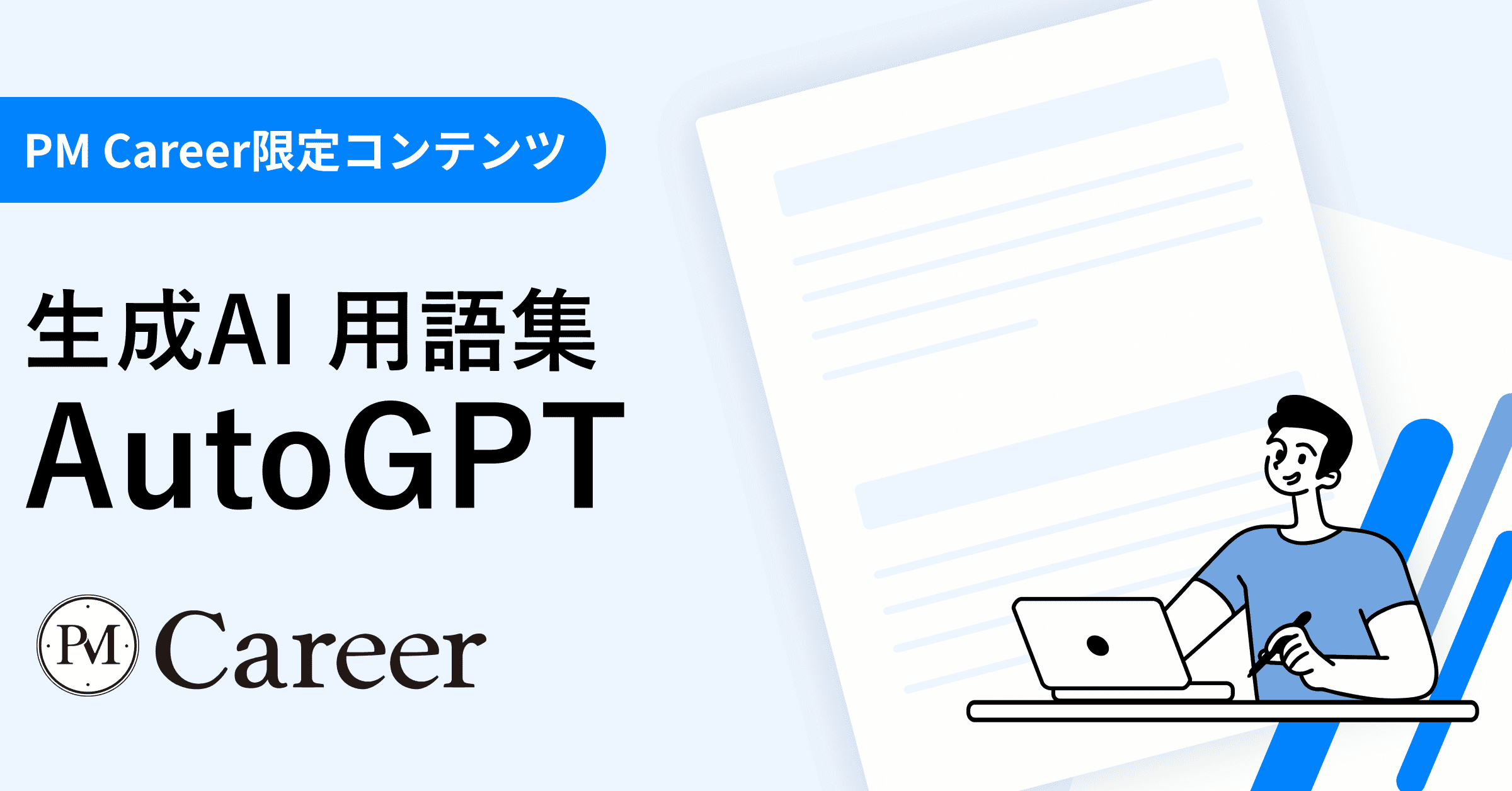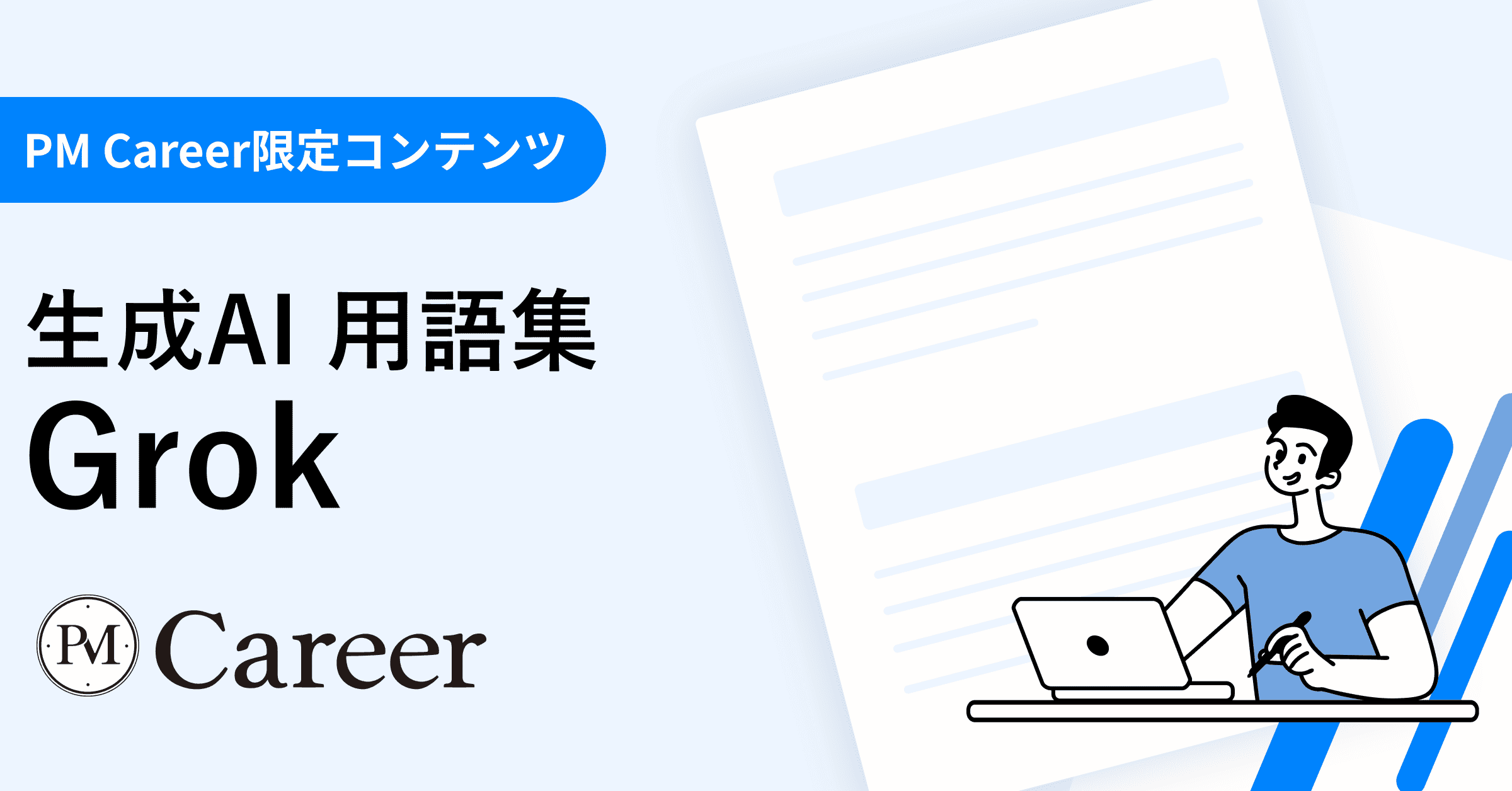
プロダクト開発
Grokとは丨生成AI 用語集
この記事の監修者佐々木真PM Career事業責任者(Xアカウント @shin_sasaki19)株式会社リクルートにて「スタディサプリ」の初期メンバーとして事業開発・プロダクトマネージャー業を担当し全国展開を達成後、SmartHRのグループ会社としてToB向けSaaS「SmartMeeting」を立ち上げ2021年3月に退任。その後PMオンラインスクール「PM School」、プロダクト開発人材の転職サイト「PM Career」の事業を運営中。プロダクト開発の知見・人材の流動性を高め、日本のプロダクト作りをぶち上げるべく尽力中。個人としてもX(Twitter)アカウントのフォロワーは3万人超え、YouTubeやPodcastでもプロダクト開発のコンテンツを発信する日本で最も有名なプロダクト開発者の1人。今すぐ転職をしたい人も、中長期的にしたい方も、PM Careerに無料会員登録をしておくことでキャリアに役立つ情報を定期的にキャッチアップすることが重要です。まだ登録されてない方はこちらからどうぞ。3分で完了します。PM Careerに無料会員登録する転職についての情報はこちらをご覧ください! プロダクトマネージャー転職完全ガイド|年収・面接対策・求人探しまで【2025年最新版】プロジェクトマネージャー 転職・完全ガイド|年収・面接対策・求人探しまで【2025年最新版】Grokとは?Grok(グロック)は、米国のテック企業 xAI(エックスエーアイ)社が開発した対話型の大規模言語モデル(LLM)ベースのチャットAIです。xAIはイーロン・マスク氏によって設立され、X(旧Twitter)との統合を視野に入れたAI開発を進めています。Grokは「真実を語るAI」を掲げており、一般的なAIよりもユーモアがあり、物議を醸す質問にも対応する“反骨精神”のある性格設定が特徴です。Grokの概要と背景xAIによる開発Grokは、2023年にElon Musk氏が創業したAI企業「xAI」によって開発されました。xAIはOpenAIやDeepMind、Tesla AIチームの出身者が集結した企業で、AIの“真実追求”と“自由な対話”を目的としています。Grokは、その中核プロダクトとして「X(旧Twitter)」との統合が進められており、ソーシャルデータとリアルタイム情報へのアクセスを活かしたAI体験が特徴です。LLM「Grok-1」シリーズGrokは、自社開発のLLM「Grok-1」や「Grok-1.5」などをベースにしており、コード処理、計算力、常識知識、推論能力などに優れています。2024年には、Mixture of Experts(MoE)アーキテクチャを採用した「Grok-1.5V」も発表され、マルチモーダル(画像・テキスト対応)にも対応し始めています。主な特徴項目GrokChatGPT(GPT-4)Claude 3開発元xAI(Elon Musk)OpenAIAnthropic特徴自由でユーモラスな対話、リアルタイムX連携汎用性、精度の高さ安全性と倫理重視LLM構成Grok-1 / Grok-1.5(MoE構成)GPT-3.5 / GPT-4Claude 1〜3マルチモーダル対応Grok-1.5V以降で対応GPT-4Vで対応Claude 3 Opusで対応Grokは、特に個性のあるAI体験やXとの連携機能において、他のチャットAIと差別化されています。X(旧Twitter)との統合GrokはX Premiumの上位プランに統合されており、ユーザーはXアカウントを通じて直接Grokを利用可能です。X上のトレンドや投稿をリアルタイムに解析しながら、質問応答や要約、トピック提案などを行えます。これにより、SNS×AIという新たなユーザー体験を提供しており、今後もXの機能に深く組み込まれていくことが見込まれます。関連用語生成AI 用語集用語LLM(Large Language Model)ChatGPTClaudeGemini


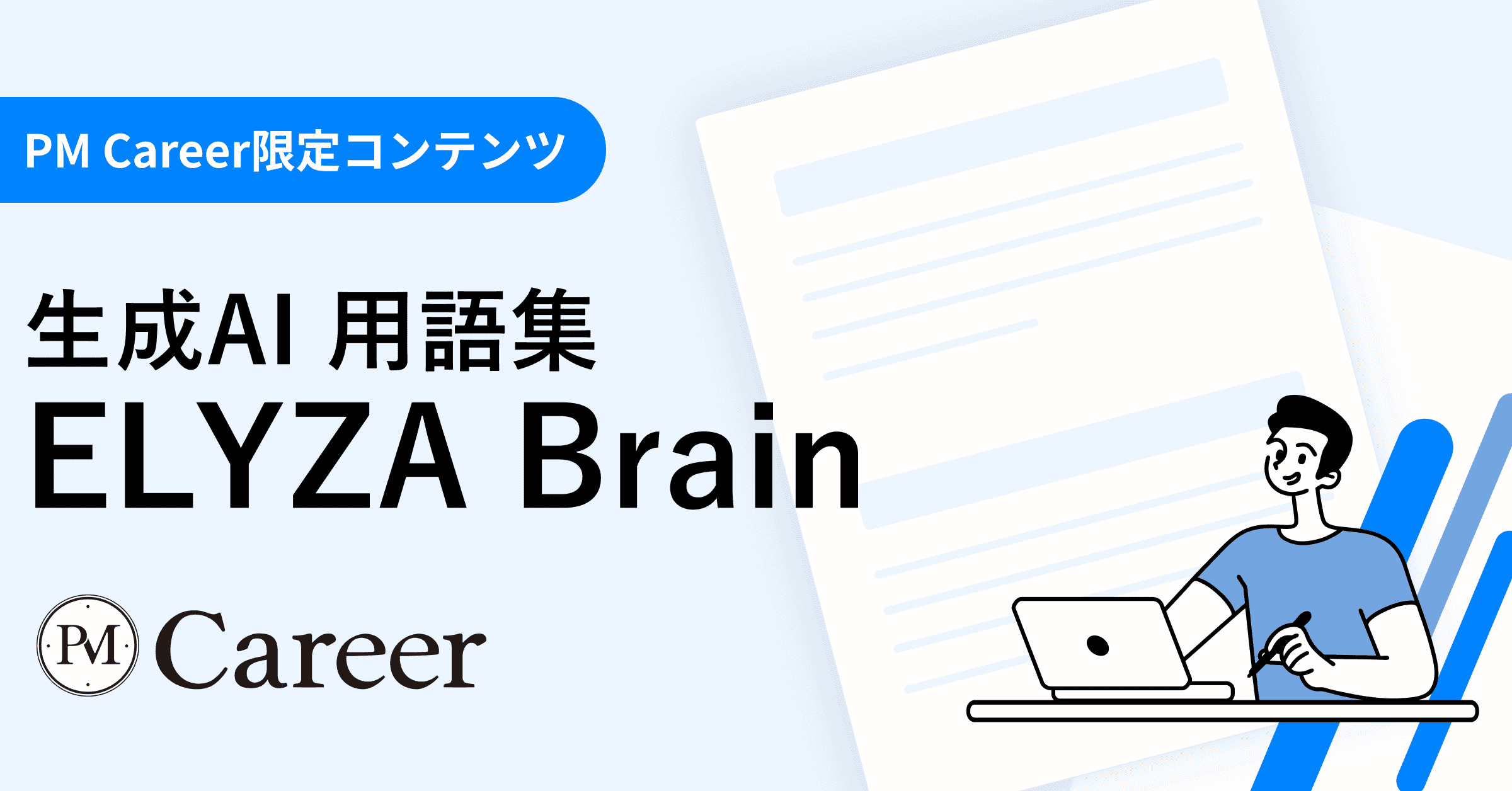
.png&w=3840&q=75)
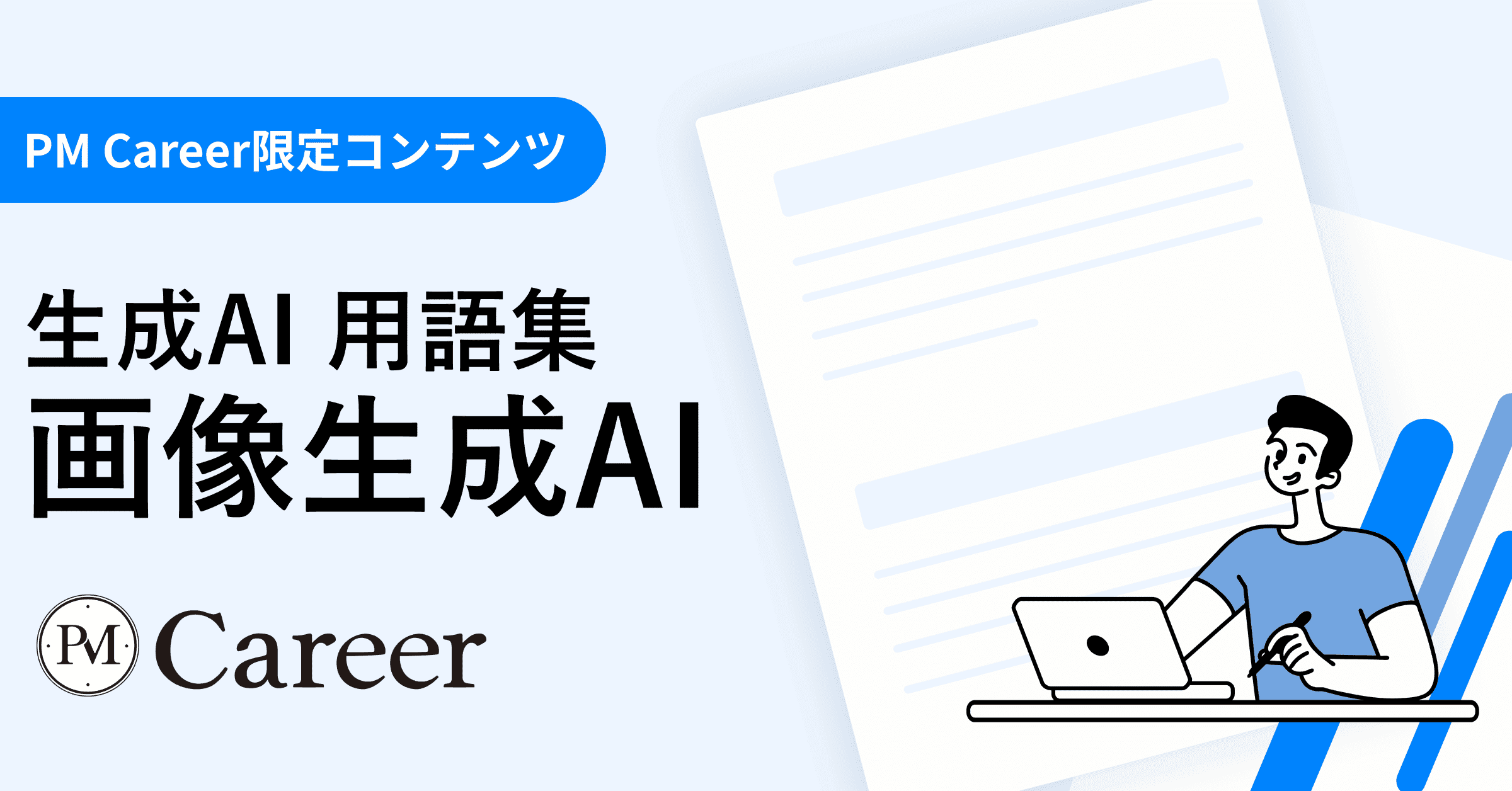
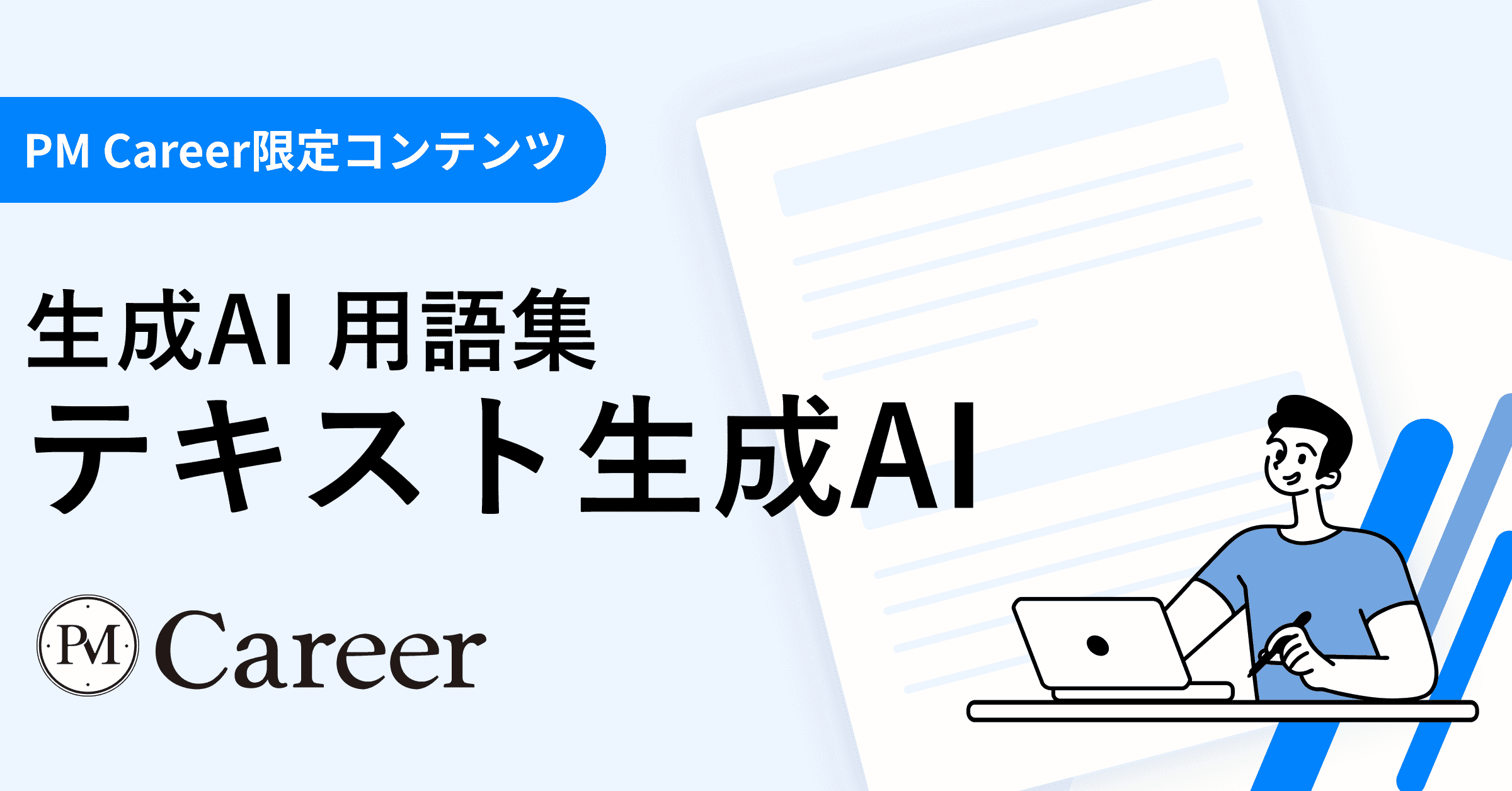
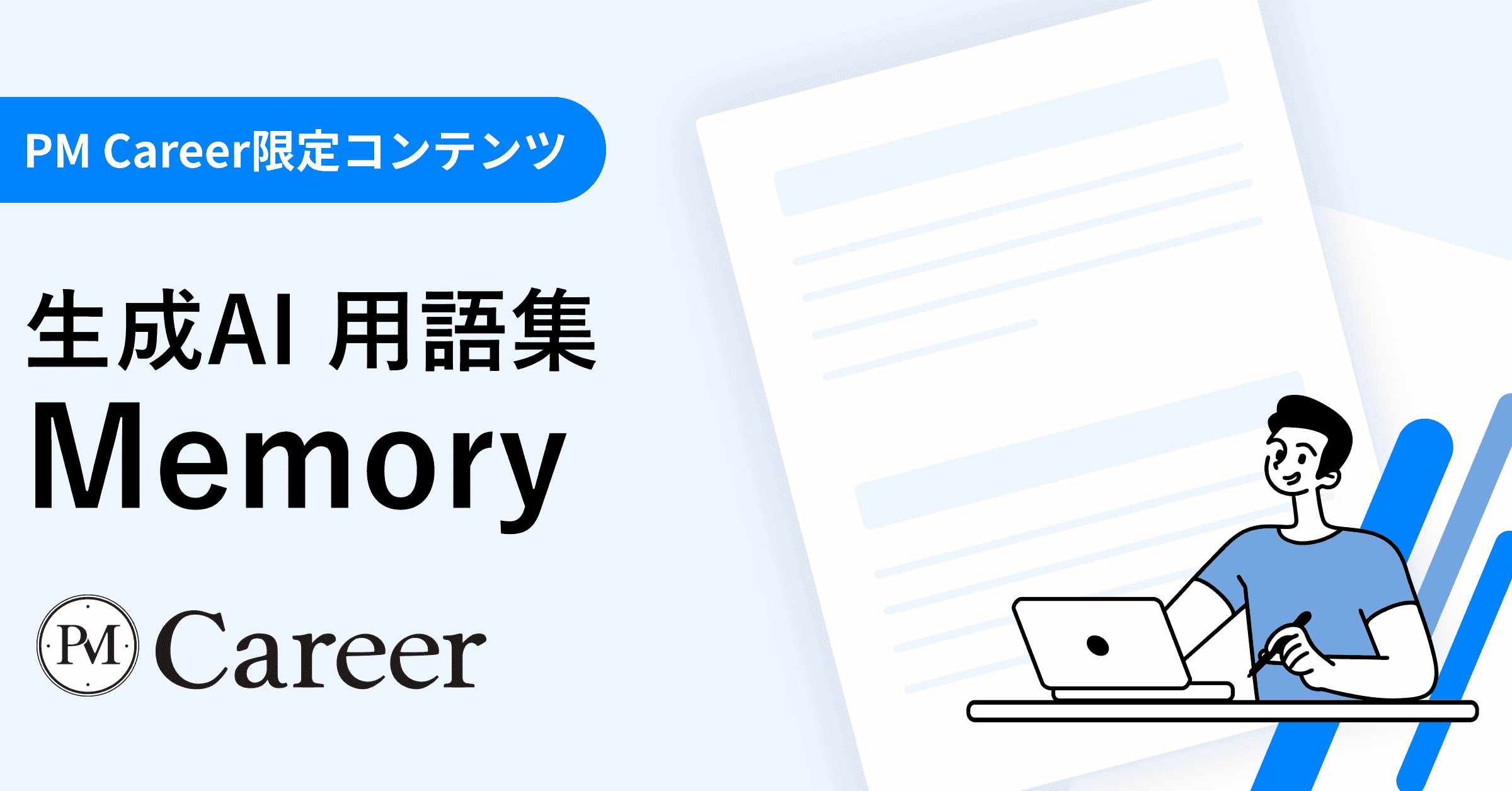
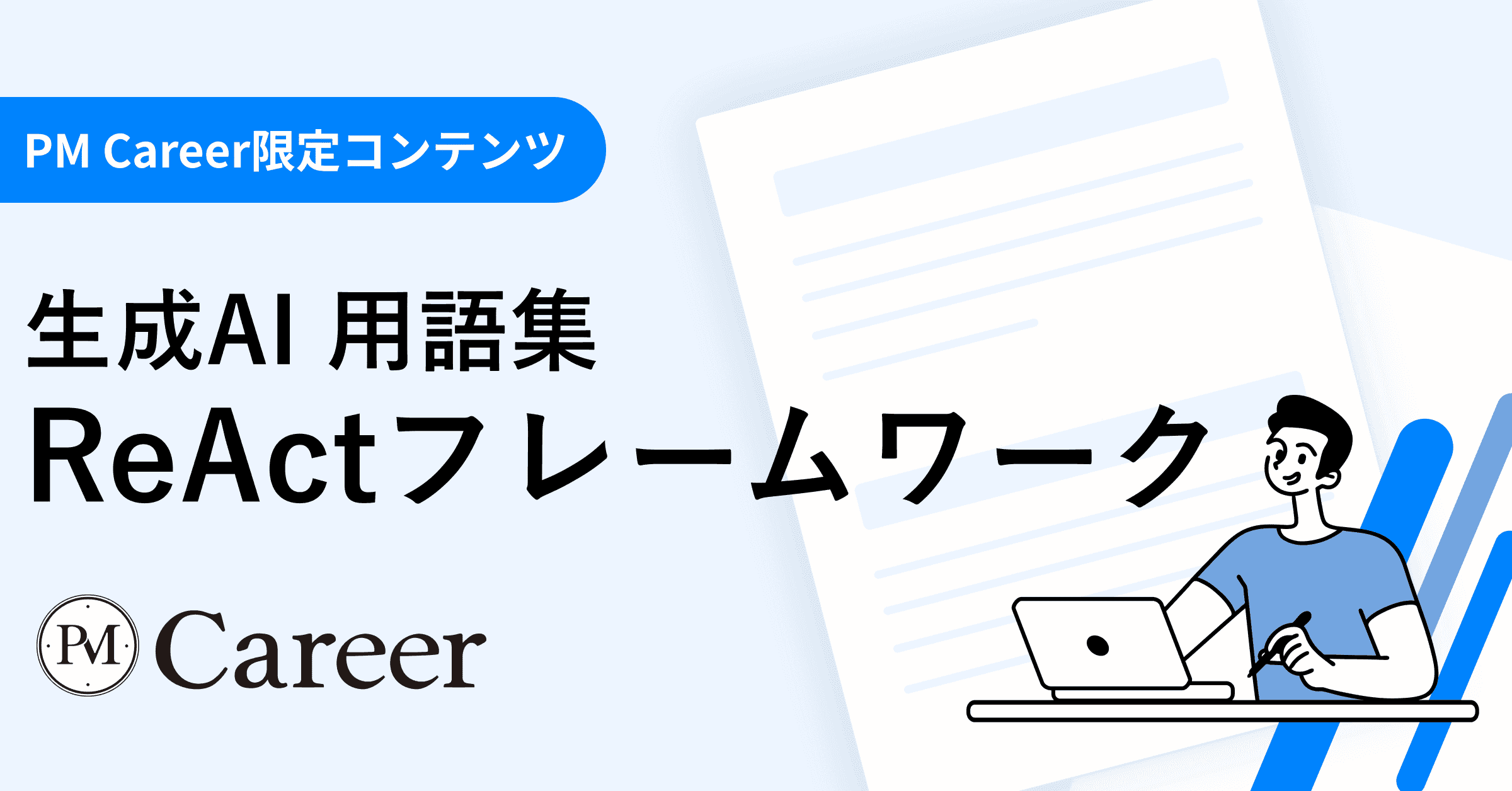
.png&w=3840&q=75)